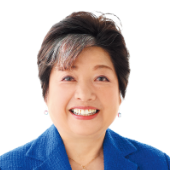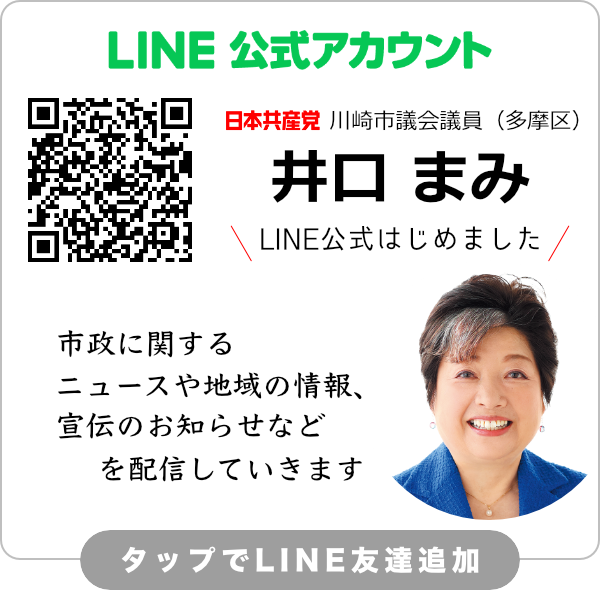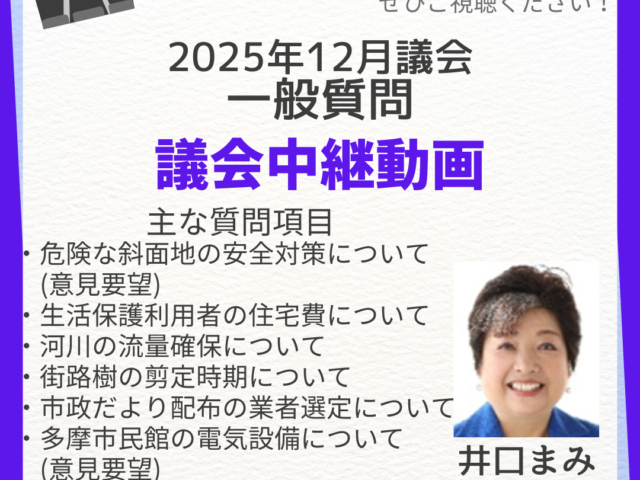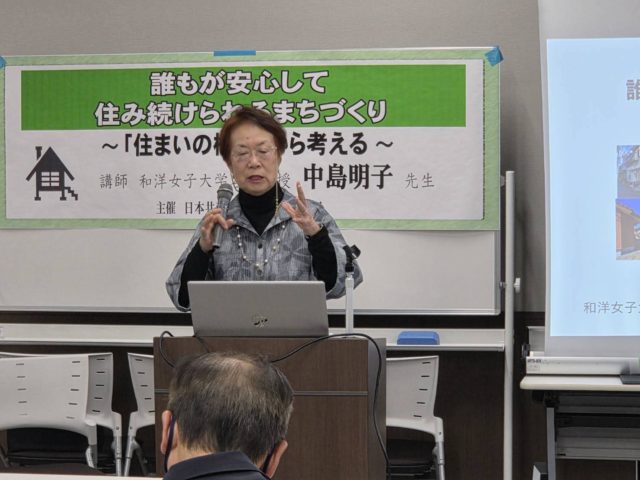熊本県に視察に来ました 一日目です
熊本に視察にきています。一日目は益城町、南阿蘇村に行きました。
益城町では議会の議長さんが2時間まるまる参加してくださり、被災状況や半年間の町や議会の取り組みを説明していただきました。
![IMG_8178[1] IMG_8178[1]](http://www.iguchi-mami.jp/wp-content/uploads/2016/10/IMG_81781_thumb.jpg) 町の中はまだ手の付いていない家もあり、胸が塞がれる思いです。議会事務局長さんが、自ら避難所の運営した経験もまじえ、たくさんの教訓、課題を話されます。「被災してほしいものはまず、飲食、トイレ、そして情報です」。その人に必要な情報が存在していること自体を届けられなということが、とても問題だと。建物の罹災証明で、半壊以上でないと、仮説にも入れず、補助金がでないため、年金暮らしの高齢者の方が家を直せなくてまだ避難所におられるという理不尽さもうかがいました。
町の中はまだ手の付いていない家もあり、胸が塞がれる思いです。議会事務局長さんが、自ら避難所の運営した経験もまじえ、たくさんの教訓、課題を話されます。「被災してほしいものはまず、飲食、トイレ、そして情報です」。その人に必要な情報が存在していること自体を届けられなということが、とても問題だと。建物の罹災証明で、半壊以上でないと、仮説にも入れず、補助金がでないため、年金暮らしの高齢者の方が家を直せなくてまだ避難所におられるという理不尽さもうかがいました。
議長さんも家は全壊。それでも毎日避難所をまわり、仮設トイレの組み立ては職員の手が足りず、議員みんなでやったそうですが、「議員は町民に頼られている」ことを実感しているそうです。
南阿蘇村ではこの地で15年間共産党の支部長さんをしておられる木下さんが、一緒にバスに乗り込んで説明してくださいました。
![IMG_8195[2] IMG_8195[2]](http://www.iguchi-mami.jp/wp-content/uploads/2016/10/IMG_81952_thumb.jpg) 山が崩れ200メートルの阿蘇大橋が一瞬にして人の命も飲み込んで崩れ去った現場は、テレビで何度も見たのに、本当に息を飲みました。この巨大な山の、頂上からずっと土砂をくずしてコンクリートをはり、国道と鉄道を掘り出して復旧するという、気の遠くなるような工事を行っています。斜面の上のほうで豆粒のようなショベルカーが一生懸命動いています。しかしこの道が復旧しなければ本当に不都合なのです。いまだに水道管も復旧せず、孤立に近い集落があります。一日も早く、とがんばっているそうですが、土石流が流れ込んだこの川にはあちこちに活断層が動いて岸が崩落し、土砂が流れ込んでいます。木下さんは「活断層は地下のどこにあるのかだれもわからないことがわかった」と言います。しかしその上流に国がダムを作る計画がありました。これだけの被害を目の前にしてまだその計画をやめないというのです。ダムに水をためたあと、また地震が起きたら、たいへんなことになると、反対運動をされているそうです。
山が崩れ200メートルの阿蘇大橋が一瞬にして人の命も飲み込んで崩れ去った現場は、テレビで何度も見たのに、本当に息を飲みました。この巨大な山の、頂上からずっと土砂をくずしてコンクリートをはり、国道と鉄道を掘り出して復旧するという、気の遠くなるような工事を行っています。斜面の上のほうで豆粒のようなショベルカーが一生懸命動いています。しかしこの道が復旧しなければ本当に不都合なのです。いまだに水道管も復旧せず、孤立に近い集落があります。一日も早く、とがんばっているそうですが、土石流が流れ込んだこの川にはあちこちに活断層が動いて岸が崩落し、土砂が流れ込んでいます。木下さんは「活断層は地下のどこにあるのかだれもわからないことがわかった」と言います。しかしその上流に国がダムを作る計画がありました。これだけの被害を目の前にしてまだその計画をやめないというのです。ダムに水をためたあと、また地震が起きたら、たいへんなことになると、反対運動をされているそうです。
活断層の真上に立っていた建物は、木の模型をくしゃっとしたようにつぶれていました。どうしたらあんな風に壊れるんだろうと思えるような新しい家も。一生懸命働いてやっと建てた家だろうに本当に悔しいだろうなあ、と思います。
![IMG_8228[1] IMG_8228[1]](http://www.iguchi-mami.jp/wp-content/uploads/2016/10/IMG_82281_thumb.jpg) 夕方になって、西原村の仮設住宅を見せていただきました。総戸数300戸、村の総合運動公園を作る予定地だった広大な土地です。おしゃべりをしていた88歳というお母さんが声をかけてくれました。「足が悪くて仮設住宅は使いにくい。家は全壊し、もう解体して何もないんだ。でもボランティアの人たちがよくしてくれる」と、難しい熊本弁で一生懸命話してくれました。
夕方になって、西原村の仮設住宅を見せていただきました。総戸数300戸、村の総合運動公園を作る予定地だった広大な土地です。おしゃべりをしていた88歳というお母さんが声をかけてくれました。「足が悪くて仮設住宅は使いにくい。家は全壊し、もう解体して何もないんだ。でもボランティアの人たちがよくしてくれる」と、難しい熊本弁で一生懸命話してくれました。
![IMG_8216[1] IMG_8216[1]](http://www.iguchi-mami.jp/wp-content/uploads/2016/10/IMG_82161_thumb.jpg) 益城町から南阿蘇村、西原村、そしてホテルのある熊本市と、バスを走らせました。ぐるっと回ってじっくり見ることができた阿蘇の自然はとてもきれいで雄大でした。阿蘇山は最近噴火もしたし、自然災害はとてもこわいものだと思います。でも、人はやっぱりここで自然といっしょに生きている。これからも生きていきたいなあと思える景色でした。
益城町から南阿蘇村、西原村、そしてホテルのある熊本市と、バスを走らせました。ぐるっと回ってじっくり見ることができた阿蘇の自然はとてもきれいで雄大でした。阿蘇山は最近噴火もしたし、自然災害はとてもこわいものだと思います。でも、人はやっぱりここで自然といっしょに生きている。これからも生きていきたいなあと思える景色でした。
二日目は熊本市です。益城町の議長さんは「ここから教訓をつかんで御市の施策にいかしていただきたい」と述べられ、そのために忙しい中視察を受け入れてくださったそうです。しっかり学び、そして考えていきたいと思います。